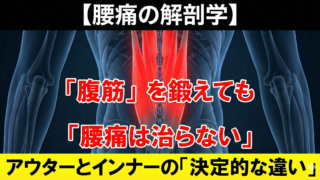 【下半身の不調】専門フロア
【下半身の不調】専門フロア 【腰痛の解剖学】なぜ、あなたの腰は「守ろうとして」悪化するのか?姿勢・股関節・筋肉の連鎖を解き明かす
「腹筋をすれば腰痛は治る」は間違いです。最新の医学では、痛みがあると脳がインナーマッスルのスイッチを切り、アウターマッスルを固めて守ろうとすることが分かっています。スウェイバック姿勢や股関節の硬さから始まる「腰痛の負の連鎖」を断ち切る方法を解説します。
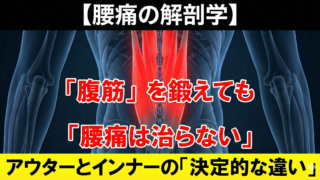 【下半身の不調】専門フロア
【下半身の不調】専門フロア  【下半身の不調】専門フロア
【下半身の不調】専門フロア 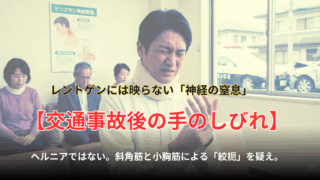 【交通事故治療】
【交通事故治療】  【上半身の不調】専門フロア
【上半身の不調】専門フロア  【交通事故治療】
【交通事故治療】 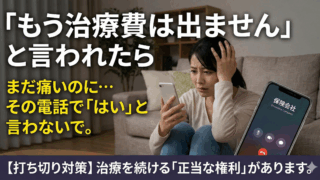 【交通事故治療】
【交通事故治療】  【院長の治療日記】
【院長の治療日記】