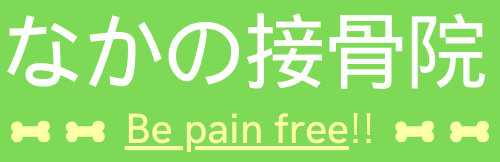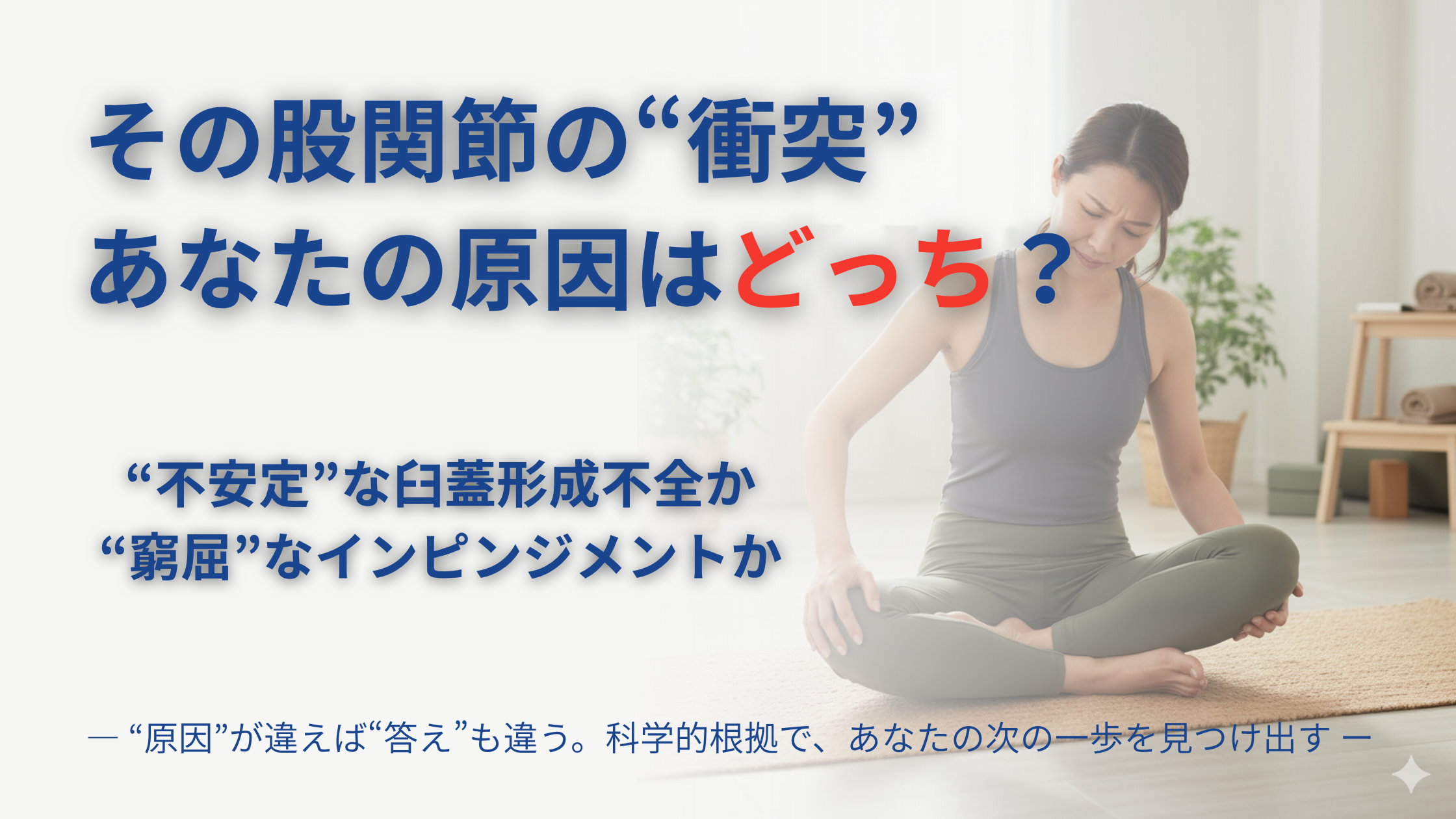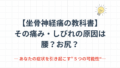「あぐらをかくと、足の付け根が詰まる…」
「深くしゃがむと、股関節に痛みが走る…」
もし、あなたが、そんな股関節の“衝突感”に悩んでいるなら、その原因は、巷で言われるような、単なる「体の硬さ」ではないかもしれません。
こんにちは。長岡京市のなかの接骨院です。
その不快な“衝突”の正体は、FAI(股関節インピンジメント)と呼ばれる、股関節の、構造的な問題かもしれません。しかし、諦めるのは、まだ早いのです。
なぜなら、FAIには、
- 受け皿が“浅い”ことによる、不安定性の物語(臼蓋形成不全)
- 受け皿が“深い”ことによる、窮屈さの物語(ピンサー・インピンジメント)
- 骨頭が“いびつ”なことによる、削り取りの物語(カム・インピンジメント)
という、3つの、全く異なる“設計図”が、存在するからです。そして、その原因によって、あなたが、本当にやるべきことは、180度、異なります。
この記事は、あなたの股関節で一体何が起きているのか、その“本当の原因”を、科学的に解き明かし、あなたの体にとって、最短・最適な、根本改善への道を、見つけ出すための、専門家による“羅針盤”です。
【第1章】あなたの股関節で起きている“衝突”の正体 ― 3つの“設計図”
この章では、まず、あなたの痛みの原因となっている可能性がある、3つの代表的な“骨の個性(設計図)”について、その違いを明確に理解します。
受け皿が“浅い”【臼蓋形成不全】
日本の変形性股関節症の約8割の原因とも言われる、最も多いタイプです。生まれつき、股関節の“受け皿”が浅いため、構造的に「不安定」な状態にあります。若い頃は強力な筋力でカバーできていますが、加齢などで筋力が低下すると、骨頭が正常な位置からズレやすくなります。この微細な“ズレ”の積み重ねが、長期的に軟骨を摩耗させ、痛みや変形を引き起こすのです。
受け皿が“深い”【ピンサー・インピンジメント】
臼蓋形成不全とは逆に、受け皿が骨頭を“覆いかぶりすぎている”タイプです。これにより、股関節を深く曲げた際に、正常な可動域に達する前に、大腿骨の首部分が受け皿の縁に物理的に“衝突”してしまいます。この「早すぎる衝突」が、関節の縁にある軟骨(関節唇)を傷つけ、痛みを引き起こします。
骨頭が“いびつ”【カム・インピンジメント】
受け皿ではなく、大腿骨頭の形に原因があるタイプです。骨頭の付け根部分に、正常にはない“骨の隆起”が存在するため、股関節を曲げた際に、その隆起が受け皿の軟骨を“削り取る”ように衝突し、損傷を引き起こします。若い男性アスリートに比較的多く見られます。
🔬
専門家コラム
A Deeper Dive into the Science
【重要】全ての道は「変形性股関節症」に通ず ― 関節唇損傷の役割
インピンジメント(ピンサー型・カム型)で傷つく「関節唇」は、関節を安定させる“吸盤”の役割を持つ、極めて重要な組織です。この吸盤が壊れると、関節は微細な不安定性を抱え、異常な圧力がかかり続けます。その結果、長期的には軟骨がすり減り、「二次性の変形性股関節症」へと進行するリスクが高まるのです。つまり、原因は違えど、どのタイプも、最終的には関節の変形という、同じ未来に行き着く可能性があるのです。
【第2章】あなたの“悩み”は、どのタイプ?
症状の“質”で見分ける、鑑別診断ガイド
ここが、この記事の核心部です。あなたの日常に潜む「悩み」を手がかりに、その原因がどのタイプに近いのか、当たりをつけていきましょう。
「股関節の詰まり感」
“グラつく詰まり”か
“ぶつかる詰まり”か?
靴下を履こうと、脚を引き寄せた瞬間を、想像してみてください。
【臼蓋形成不全】
もし、その詰まりが、動きの“途中”で、どこか“ハマりが悪い”ような、グラつくような感覚を伴うなら、それは、臼蓋形成不全による不安定性が原因かもしれません。
【インピンジメント】
もし、その詰まりが、動きの“最後”で、「これ以上は曲がらない」という、骨と骨が、コツンとぶつかるような硬い感覚なら、それは、インピンジメントによる物理的な衝突の可能性が高いでしょう。
「あぐらがかけない」
“不安な硬さ”か
“物理的な壁”か?
あぐらをかこうと、股関節を開く時、何を感じますか?
【臼蓋形成不全】
もし、その硬さが、「なんだか怖い」「力が抜けてしまいそう」といった、不安感を伴う筋肉の緊張から来ているなら、それは、臼蓋形成不全の不安定性を、脳が無意識に守ろうとしている“防御反応”かもしれません。
【インピンジメント】
もし、その硬さが、痛みと共に、明確な“物理的な壁”にぶつかるような感覚なら、それは、インピンジメントが、それ以上の可動を、許していないサインです。
【第3章】あなたが、本当にやるべきこと
― “原因”が違えば、“答え”も違う ―
もし、あなたの原因が
「不安定性(臼蓋形成不全)」にあるなら
あなたのアプローチの主眼は【安定化】です。グラつく関節を、内側から支える“インナーマッスル”を目覚めさせ、関節を“中心”に保つことが、最優先課題となります。過度なストレッチは、不安定性を助長するリスクがあるため、慎重に行う必要があります。
【セルフケア例】クラムシェル
横向きに寝て、膝を軽く曲げます。かかとをつけたまま、上側の膝を、ゆっくりと開閉し、お尻の横の筋肉(中殿筋)を意識します。この運動は、股関節に負担をかけずに、重要な安定筋を鍛えることができます。
もし、あなたの原因が
「窮屈さ(インピンジメント)」にあるなら
あなたのアプローチの主眼は【解放と再教育】です。衝突を引き起こしている、過緊張した前側の筋肉(腸腰筋など)を解放し、関節がスムーズに動ける“スペース”を作ることが、第一歩です。その上で、サボっている後ろ側(お尻)の筋肉を再教育し、正しい動きのパターンを、体に思い出させます。
【セルフケア例】腸腰筋のストレッチ
片膝立ちになり、後ろの足の付け根を、ゆっくりと前に突き出すようにして伸ばします。この時、腰を反らさず、お腹に軽く力を入れるのがポイントです。
【結論】手術の前に、“希望”はある
この記事を通して、あなたの股関節の悩みが、決して、漠然としたものではなく、明確な、科学的“原因”に基づいていることを、ご理解いただけたかと思います。
骨の“形”は、変えられません。しかし、その“形”と、どう付き合っていくか。筋肉のバランスを整え、正しい動きのパターンを再学習することで、痛みを引き起こしている“衝突”そのものを、回避することは、十分に可能なのです。
その“再学習”のプロセスを、最短・最適に進めること。それこそが、我々、徒手療法の専門家の、本当の役割です。
もし、あなたが、ご自身の体の“設計図”と、本気で向き合いたいと願うなら。我々の扉は、いつでも、あなたのために開いています。
\LINEでの個別相談・お問い合わせ専用です/
\お電話はこちらから/
- 股関節全体の“哲学”を、もっと、深く、理解したい方へ
→ 【股関節の教科書】全ての不調は、中心軸のズレから始まっていた - 将来的な「変形」が、不安な方へ
→ 【変形性股関節症】40代からの股関節痛、本当の原因と治し方 - “お尻”や“足のしびれ”も、気になる方へ
→ 【坐骨神経痛の教科書】その痛み、原因は腰?お尻?