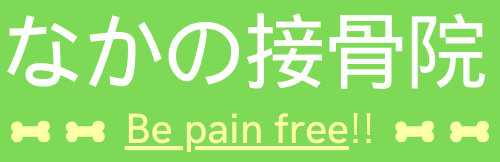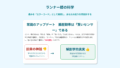膝の内側が痛む、「鵞足炎(がそくえん)」。
もしあなたが、「原因は“使いすぎ”だから、安静とストレッチしかない」と考えているなら、そのアプローチは、問題の半分しか見ていないかもしれません。
こんにちは。長岡京市のなかの接骨院です。
この記事は、巷に溢れる一般的な情報とは一線を画す、あなたの鵞足炎の“真犯人”を見つけ出すための、科学的な「鑑別診断ガイド」です。
ご存知でしたか?
「鵞足」とは、実は、それぞれ全く違う役割を持つ、【縫工筋・薄筋・半腱様筋】という、3つの筋肉の腱が集まる場所の、総称です。
そして、あなたの痛みの“主犯”が、この3つのうちのどれなのかは、あなたが「どんな動きで痛むか」によって、科学的に推測することができるのです。
- ランニングの“振り出し”で痛むのか?
- ボールを“蹴る瞬間”に痛むのか?
- それとも、“あぐらをかく”ような動きで痛むのか?
この記事を読むことで、あなたは、ご自身の痛みの、より深い原因を理解し、なぜ、これまであなたの努力が報われなかったのかを知ることができます。
さあ、根本改善への、本当の第一歩を、ここから始めましょう。
【解剖学】そもそも「鵞足」とは何か? ― 3つの筋肉が集まる“交通の要衝”
鵞足炎とは?
膝の内側にある、3つの異なる筋肉の腱が集まる場所「鵞足(がそく)」に、炎症が起こるスポーツ障害です。
単なる“使いすぎ”ではなく、これらの筋肉の“チームワークの崩壊”が、痛みの本当の原因です。
まず、あなたの痛みの“現場”となっている、「鵞足(がそく)」について、正確に理解することから始めましょう。
その名前の由来は、縫工筋・薄筋・半腱様筋という3つの筋肉の腱が、膝の内側の一点に集中して付着する様子が、 “ガチョウの足”のように見えることから名付けられました。
そして、ここが最も重要なポイントです。これら3つの筋肉は、それぞれが全く異なる役割(股関節を曲げる・閉じる・伸ばす)を担っており、膝の“ねじれ”を防ぐ、重要な安定化機構として機能しています。
- 縫工筋(ほうこうきん)
骨盤の前から始まり、股関節を「曲げ・開き・外に回す」動きを担います。 - 薄筋(はっきん)
骨盤の下(恥骨)から始まり、股関節を「閉じる」動きを専門とします。 - 半腱様筋(はんけんようきん)
骨盤の後ろ(坐骨)から始まり、股関節を「伸ばす」動きを担います。
つまり、「鵞足」とは、股関節のあらゆる動きを制御する、方向の違う3本の“手綱”が、たった一点に集約された、極めて重要な“交通の要衝”なのです。
そして、これらの筋肉は、単に膝を曲げるだけでなく、膝から下が外側にねじれないようにブレーキをかける、重要な「回旋安定化機構」としての役割も担っています。
【本題】あなたの“主犯”はどの筋肉? ― 動きでわかる鑑別診断チャート
さて、ここからがこの記事の“本題”です。
あなたの膝の内側の痛みを引き起こしている“主犯”が、3つの筋肉のうち、どれである可能性が高いのか。あなたが痛みを感じる“特定の動き”を手がかりに、当たりをつけていきましょう。
以下の表で、ご自身の症状に最も近いものを、確認してみてください。
| こんな動きで痛む | 最も疑わしい“主犯” | なぜなら…(科学的根拠) |
|---|---|---|
| ランニングで、脚を後ろに振り出す時 | 半腱様筋 | この筋肉は、地面を蹴る際の、股関節を伸ばす動きで最も働きます。 |
| サッカーのインサイドキックや、方向転換で踏ん張る時 | 薄筋 | この筋肉は、脚を内側に閉じる動きを専門としています。 |
| あぐらをかいたり、ズボンを履くために膝を開く時 | 縫工筋 | この筋肉は、股関節を「曲げ・開き・外に回す」という、特殊な動きを担います。 |
【解決策】“主犯”に合わせた、正しいアプローチとは?
ご自身の痛みの“主犯”に、当たりをつけることはできたでしょうか。
この鑑別が重要なのは、原因となる筋肉が違えば、取るべきアプローチも、全く異なってくるからです。
だからこそ、「鵞足炎には、このストレッチ」といった、画一的な情報が、あなたの症状を、必ずしも改善させるとは限らないのです。
- 半腱様筋
- 薄筋
- 縫工筋
半腱様筋が“主犯”の場合
この筋肉は、太ももの裏側を構成する「ハムストリングス」の、重要な一員です。
したがって、ハムストリングス全体の柔軟性を高めるアプローチは有効ですが、それだけでは不十分です。なぜなら、ハムストリングスの過剰な緊張は、多くの場合、骨盤が前に倒れすぎる「骨盤前傾」という、より大きな問題の結果として、引き起こされているからです。骨盤の位置を正常化させずして、根本的な解決はあり得ません。
薄筋が“主犯”の場合
この筋肉は、太ももの内側にある「内転筋群」に属します。
内転筋群が硬くなる原因は様々ですが、スポーツ動作においては、特に、体幹(コア)の不安定性が、大きく関与します。体の軸がブレるのを、内転筋群が、必死に内側に締めることで、代償しようとした結果、過労状態に陥っているのです。体幹を安定させるアプローチが、不可欠となります。
縫工筋が“主犯”の場合
この筋肉は、人体の筋肉の中で、最も長いという特徴を持ち、非常に複雑な走行をします。
縫工筋が原因となる痛みは、筋肉そのものの硬さというよりは、それが通過する、他の筋肉や筋膜との“滑走性(滑りの良さ)”が悪化しているケースが、非常に多いです。この場合、単純なストレッチよりも、専門家による「筋膜リリース」のような、滑走性を改善させるアプローチが、特に有効となります。
結論 根本改善とは、“チームワーク”を取り戻すこと
ご自身の痛みの“主犯”を特定することは、根本改善への、重要な第一歩です。
しかし、本当のゴールは、特定の筋肉だけを緩めることではありません。
最終的に目指すべきは、鵞足を構成する3つの筋肉が、再び互いに協調し、膝の安定性のために正しく機能する“チームワーク”を取り戻すことです。
そして、そのためには、痛む膝だけでなく、その“内戦”の引き金となった、足元から股関節、体幹まで含めた、全身の運動連鎖を評価できる、専門家の目と手が必要不可欠となります。
もし、あなたが本気で、この“内戦”を終結させたいと願うなら、ぜひ一度、私たちにご相談ください。